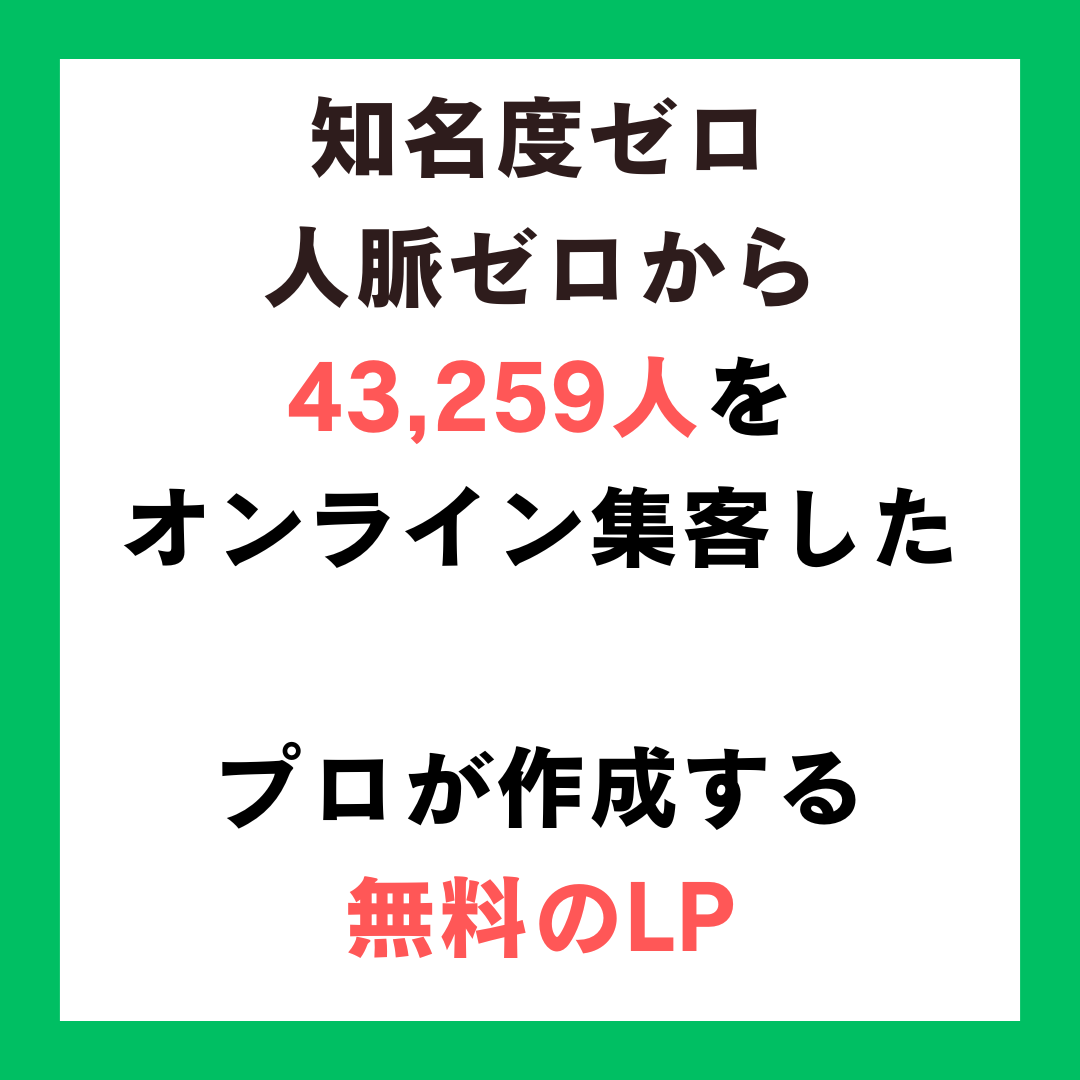「やっぱウチの会社、銀行から全然評価されてないな…」
決算書を見つめながら、ため息をつく日々。
事業は順調に伸びてるはずなのに、いざという時の融資がなかなか通らない。
新しい設備投資をしたい、事業を拡大したい、そう思っても、銀行からの評価が低ければ何もできない。
「どうしてなんだろう?」
それは銀行が融資を判断する材料、決算書に”載せてはいけない”数字があるからなんだ。
今回は、銀行が「この会社はヤバい」と判断する、決算書に潜む危険なサインと、逆に「この会社なら貸してもいい」と評価されるポイントを話していこう。
銀行融資に落ちる社長が絶対にやっている「ヤバい勘定科目」の正体
銀行は、融資を審査する際に、会社の儲けを示す損益計算書(P/L)よりも、会社の財産状況を示す貸借対照表(B/S)をはるかに重視する。
なぜなら、銀行が知りたいのは「この会社、返済能力はあるか?」ではなく、「この会社、潰れないか?」だからだ。
そのB/Sの中に、銀行から「この会社は信用できない」と判断される致命的なサインがいくつかある。
1. 仮払金・仮受金、そして多額の雑勘定
これらは本来、一時的な処理に使う勘定科目だ。
決算時にはゼロにするのが当たり前。
それなのに、多額の金額が残っていたり、内容が不明瞭なまま放置されていたりすると、銀行は「この会社の経理はズサンだな」と判断する。
最悪の場合、「何か隠してるのでは?」と不正を疑われる原因にもなりかねない。
俺も起業したばかりの頃、経理の知識がなくて雑費にいろんなものをまとめてしまっていた。
その結果、銀行の担当者から「これは何のお金ですか?」と厳しく追及され、冷や汗をかいた経験がある。
2. 社長への貸付金・立替金
これが一番致命的だ。
銀行からの借り入れがある状態で、会社の資金が社長個人に貸し付けられていると、銀行は激怒する。
これは「迂回融資」とみなされ、「うちが貸した金を、社長の遊びに使ってるんじゃないか?」と疑われる。
考えてもみてほしい。友達から「お金を貸して欲しい」と頼まれて貸したとしよう。その後に友達がパチンコ屋から出てきたところを目撃。
いくら友達が「いや、自分の金で遊んでるだけだよ🤣」とか言い訳されても納得できないよな!
それと一緒!
「いやいや、ちゃんと返しますよ!」と言っても無駄だ。
会社と社長のお金を区別できない経営者は、銀行からの信頼を失う。
俺の知り合いの社長は、これで融資を断られた。
税理士に「経費にならない個人的な支払いは貸付金で処理しておきましょう」と提案されて、深く考えずにやっていたらしい。
結果、銀行からは「会社の資金を私物化している」と烙印を押され、事業の継続が危ぶまれる事態になった。
3. 会員権・保険積立金
会社に借金がある、または赤字なのに、ゴルフやリゾートの会員権を持っている。
銀行からすれば、「お金の使い方を間違えている」としか見えない。
「お金に困ってるなら、なぜそんな贅沢品に投資するんだ?」と、経営者としての資質を疑われる。
また、社長の退職金目的で積み立てる保険も同様だ。
借金がある状況での積み立ては、「資金効率が悪い」と判断される。
万が一、会社が倒産すれば、その積立金も受け取れない可能性すらある。
赤字でも銀行の評価が上がる「最強の勘定科目」
「じゃあ、逆に銀行に好かれるにはどうすればいいんだよ?」
そう思ったキミに、朗報だ。
赤字であっても、銀行からの評価がグンと上がる「最強の勘定科目」がいくつかある。
1. 利益剰余金(内部留保)
これは、これまでの利益の積み重ねだ。
言わば「会社の体力」。
ここが潤沢にあれば、多少の赤字が出ても倒産することはないと銀行は考える。
経営者は、短期的な利益だけでなく、この「内部留保」をいかに増やしていくかという視点が重要だ。
2. 現金(キャッシュ)
「Cash is king(キャッシュは王様)」という言葉があるように、手元に現金が多い会社は強い。
赤字でも現金さえあれば倒産しない。
銀行もこの事実をよく知っているから、キャッシュが豊富な会社には積極的に融資しようとする。
「借金してまで現金を貯めてどうするんだ?」
そう批判されるかもしれないが、このキャッシュこそが、いざという時に会社を守ってくれる盾になる。
3. 借入金
意外かもしれないが、借金が多いこと自体は問題ではない。
むしろ、多額の借入金があることで、銀行は会社と「同じ船に乗っている」状態になる。
会社が潰れたら銀行も困る。だからこそ、銀行は会社の存続のために積極的に支援してくれる可能性が高くなる。
安易に繰り上げ返済をするのではなく、借りたお金を元手に事業を拡大していく経営者の方が、銀行からの評価は高いんだ。
批判的なキミへ。「知っててもやらない」のは、もはやリスクだ
「ああ、そんなこと言っても、税理士に任せてるから大丈夫でしょ」
「いちいち細かいことまで気にしていられないよ。俺は経営に専念するんだ」
そう思ったキミの気持ち、わかる。
俺も昔はそう思っていた。
でも、それは「自分の会社の状態を自分で把握していない」ということと同じだ。
税理士はあくまで会社の数字を処理してくれる専門家であって、経営の責任はキミ自身にある。
もし、税理士が言われるがままに「ヤバい勘定科目」を計上していたら、どうなるだろうか?
銀行からの信頼を失い、事業拡大のチャンスを逃すことになる。
これは「税理士のせい」ではなく、「経営者であるキミ自身の責任」だ。
アドラー心理学でいうところの「課題の分離」ってやつだ。
会社の数字を理解し、経営の課題と自分の課題をしっかり分けて考えられる経営者こそ、銀行からも信頼され、事業を成功させることができる。
だから、キミも「知ってるだけ」で終わらせず、今日から一歩踏み出してほしい。
まとめ:経営者よ、数字から目を背けるな
今の事業に不満がある、もっと成長させたい、そう思うなら、まずは自分の会社の数字をしっかり見てみようぜ。
何がヤバくて、何が良いのか。
それを理解するだけで、銀行からの評価は驚くほど変わる。
もし、まだ会社の数字に自信がないなら、簿記3級の勉強から始めてみるのもいいかもしれない。
会社の数字が読めるようになると、日々の経営判断の精度が格段に上がる。
現状に不満を言っていても、何も変わらない。
行動を起こして、自分の会社の未来に責任を持とうぜ。
俺はキミの挑戦を、心から応援している。
一緒に、現状を打破する一歩を踏み出そうぜ!