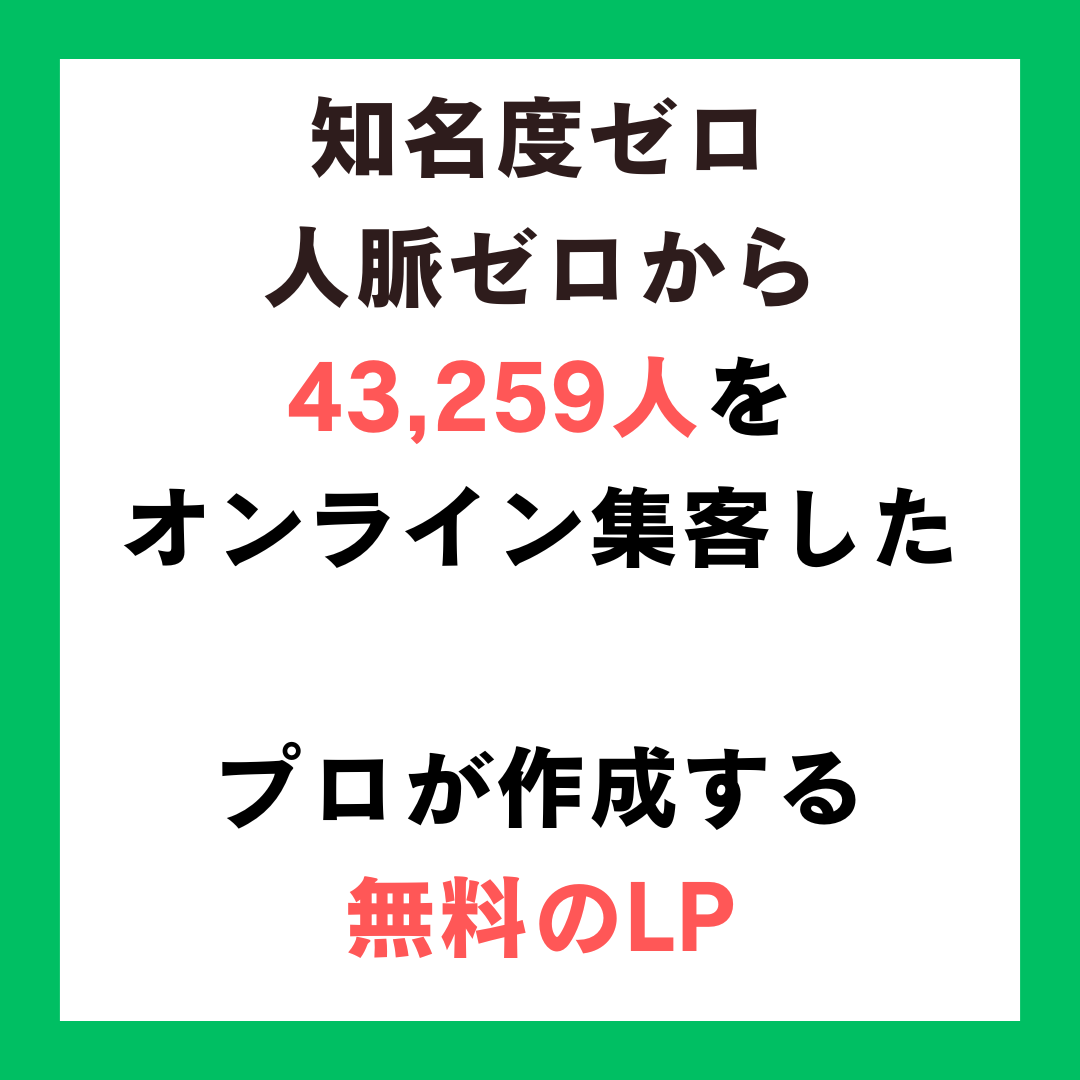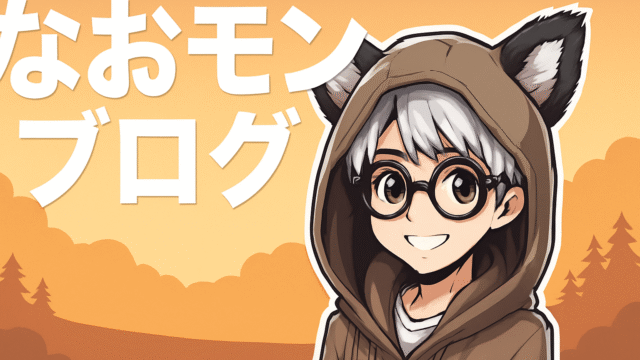「うちの会社ってどうやって給料決めてるんだろう…」
「頑張ってるのに、なんで給料上がらないんだろう?」
20代、30代のビジネスパーソンの皆さん、こんな風に思ったことはありませんか?実は、中小企業の給料決定って、意外と複雑で、社長の「肌感覚」だけで決めているわけではないんです!
今回は、普段は明かされない中小企業の給料決定の裏側を、具体的な指標を交えながら徹底解説します。
この記事を読めば、あなたの給料がどう決まっているのかが分かり、今後のキャリアアップや給料交渉にも役立つヒントが見つかるはずです!
ぶっちゃけ、中小企業の給料決定って難しい!でも基準はある
これは、僕が普段からお話ししていることですが、中小企業の給料決定は本当に難しいんですよ。
大企業のように明確な評価制度が確立されていないケースも多く、「どうすれば社員が納得して、会社も成長できるのか?」という悩みを抱える経営者は少なくありません。
しかし、闇雲に決めているわけではありません。いくつかの重要な指標を基に、総合的に判断しているんです。今回は、その具体的な指標と、知り合いの会社で実践している給料決定プロセスを大公開します!
給料を決める3つの重要指標
まず、給料を決める上で欠かせない3つの指標をご紹介します。
1. 一人当たり粗利益:「あなたが会社にどれだけ貢献しているか?」の指標
皆さんは、自分の給料の何倍の粗利益を稼ぎ出すべきだと思いますか?
先を読み進める前に、ちょっとだけ考えてみてください。
正解は…「3倍」です!
つまり、もしあなたが年収600万円欲しいなら、会社に1800万円の粗利益をもたらす必要があるということです。これはあくまで目安ですが、「自分が会社に対してどれだけ価値を生み出しているか」を測る重要な指標になります。
さらに、「1人当たり年間粗利益1000万円」という数字も意識してみてください。これは、社員1人あたりが最低限稼ぎ出すべき粗利益の目安です。これに満たない場合、そもそも社員を増やすこと自体が会社の経営を圧迫する可能性もあるんです。
2. 労働分配率:「人件費が粗利益に対して適切か?」の指標
労働分配率とは、「人件費 ÷ 粗利益」で算出される数値で、会社が稼いだ粗利益のうち、どれだけ人件費に回しているかを示す指標です。
ここでポイントなのが、「人件費」には給料だけでなく、社会保険料や福利厚生費なども含まれるということ。これらを含めた人件費が粗利益の40%〜50%に収まっているのが理想的と言われています。中小企業では50%を超えるケースも少なくありませんが、この範囲に収めることが健全な経営に繋がります。
数値例として、このような会社があるとしましょう。
- 売上:1億円
- 原価(変動費):4,000万円
- 粗利益:6,000万円
- 人件費(給与+法定福利費+福利厚生費):2,700万円
- その他経費:2,400万円
- 経常利益:900万円
この場合、労働分配率は 2,700万円÷6,000万円=45% となり、理想的な範囲に収まっていますね。
3. 経常利益:「会社がきちんと利益を出せているか?」の指標
経常利益とは、会社の通常の事業活動で得られた利益のことです。この経常利益は、粗利益の10%〜20%が適正だと言われています。
先ほどの例で言えば、粗利益が6,000万円なので、経常利益は600万円〜1,200万円が目安となります。例で挙げたこの会社では900万円なので、これも適正範囲に収まっています。
これらの指標をバランス良く見て、会社の経営状況と照らし合わせながら給料をコントロールしていくことが重要なんです。
会社が実践する「年俸&決算賞与」の給料決定術
では、これらの指標を踏まえ、僕の知り合いの会社が実際にどのように給料を決めているのか、その秘密を公開します。
その会社では、毎月の給料は個々の社員の仕事内容や役職に応じて手当などを決めています。しかし、それだけでは社員のモチベーションを最大限に引き出すのは難しい。そこで、重要になるのが「決算賞与」です。
役員会議で年俸を決定!
その会社では、毎年の決算時に役員全員で社員一人ひとりの「年俸」を決定します。
- 去年の年収を確認: まずは、対象社員の去年の年収を確認します。
- 今年の貢献度をプレゼン: 各役員が、その社員の今年の働きぶりや貢献度を具体的なエピソードを交えながらプレゼンします。この時、役員間で意見が分かれることもありますが、それぞれの視点から意見を出し合うことで、より多角的に社員の貢献度を評価できます。
- 最終的な年俸を決定: 全員の意見を総合し、社長が最終的な年俸を決定します。
例えば、社員Aさんの去年の年収が600万円だったとします。役員会議で議論した結果、今年の貢献度を評価して年俸900万円に決定したとしましょう。
決算賞与でズバッと還元!
年俸が決まったら、あとはシンプルです。
- 月々の給料: 例えば、年俸900万円の場合、月々の給料が55万円だとすると、年間で660万円になります。
- 決算賞与: 年俸(900万円)から月々の給料の合計(660万円)を引いた差額の240万円を、決算賞与として還元します。
この方法の最大のメリットは、会社に利益が出た分をダイレクトに社員に還元できる点です。月々の給料を固定しすぎると、会社が儲かっても社員に還元しにくい。でも、決算賞与で調整することで、会社の成果が社員の給料に直結し、モチベーションアップにも繋がります。
中小企業で「評価制度」がうまくいかない理由
「ウチの会社では、評価制度があるけどそれって意味ないの?」
「評価制度作らなくていいの?」
そう思われた方もいるかもしれません。実は、中小企業で評価制度を完璧に運用するのは非常に難しいんです。
なぜなら、中小企業は常に変化し、成長していくものだからです。会社の規模が大きくなったり、事業内容が変わったりすれば、それまでの評価制度が現状に合わなくなるのは当然のこと。その都度、評価制度を見直すとなると、莫大な時間と労力がかかりますし、「結局、前のが何だったんだ…」という不満にも繋がりかねません。
だからこそ、知り合いの会社では「毎年変わる可能性がある評価制度」に固執せず、シンプルに「年俸を役員会議で決めて、決算賞与で調整する」という方法を採用しています。これにより、社員の貢献度を柔軟に評価し、会社の利益を適切に還元することが可能になるのです。
知っておくと得する「決算賞与」のメリット!
決算賞与は、社員への還元だけでなく、会社にとっても大きなメリットがあります。
- 銀行評価への影響が少ない: 決算賞与は、損益計算書の「特別損失」の項目に計上されるため、銀行が評価する「営業利益」には影響を与えにくいという特徴があります。これにより、銀行からの評価を下げずに社員へ利益を還元できます。
- 節税対策にもなる: 利益が出すぎた場合、その一部を決算賞与として社員に還元することで、法人税の節税にも繋がります。
もちろん、利益が出すぎて社員の期待値が上がりすぎるのも考えものなので、一部は節税商品などで繰り延べるなど、バランスを見ながら調整することも重要です。
まとめ:あなたの頑張りはこうやって評価されている!
いかがでしたでしょうか?
今回は、中小企業における給料決定のリアルな裏側を、具体的な指標やとある会社の事例を交えて解説しました。
- 1人当たり粗利益は3倍、年間1000万円以上を目指す!
- 労働分配率は40%〜50%が理想!
- 経常利益は粗利益の10%〜20%を目指す!
- 月々の給料は安定させ、余った利益は決算賞与で社員に還元!
あなたの頑張りは、決して無駄になっていません。これらの指標と会社の状況を理解することで、自身の市場価値を高め、より良いキャリアを築くためのヒントが見つかるはずです。
もし「もっと詳しく知りたい!」という方がいれば、ぜひコメントで教えてくださいね!