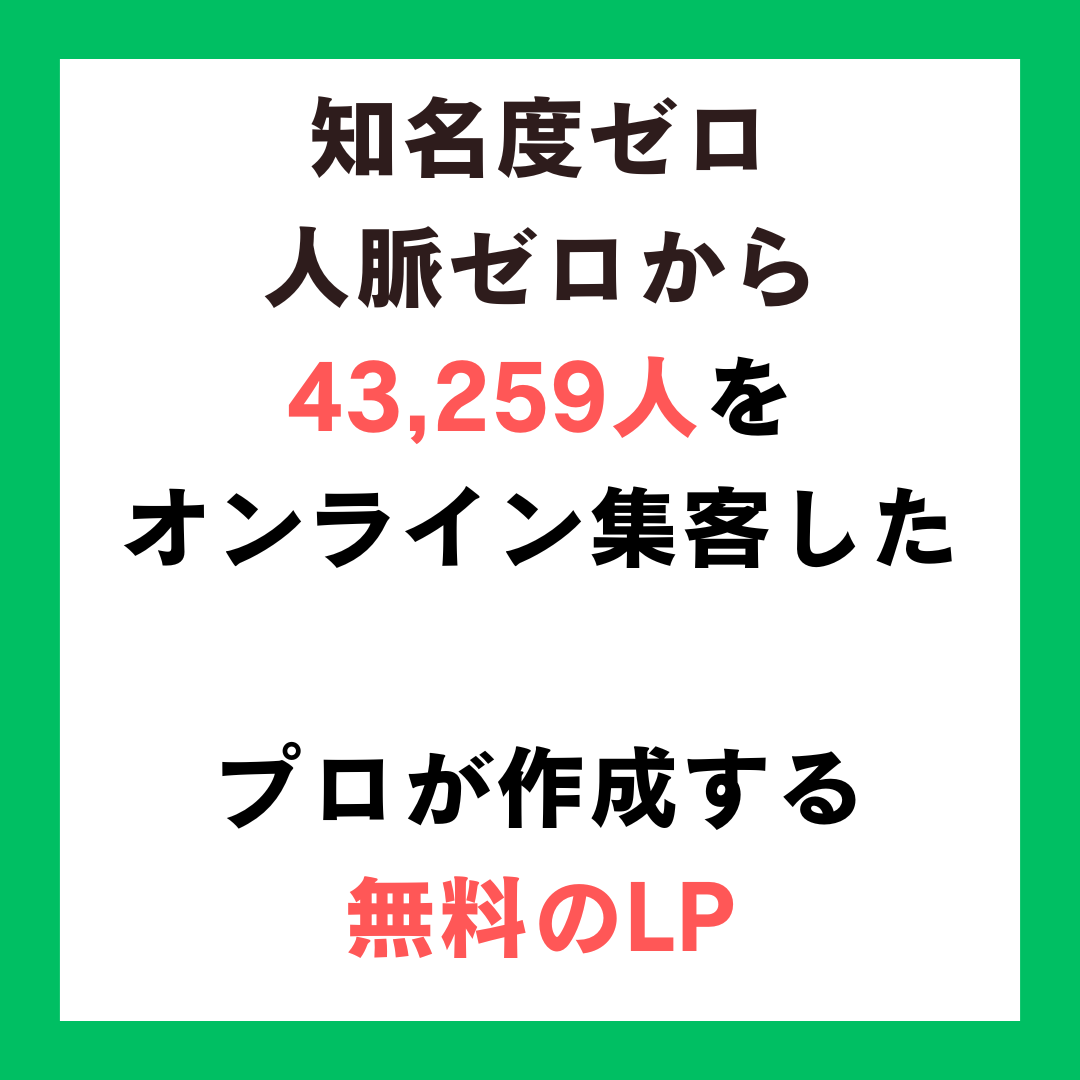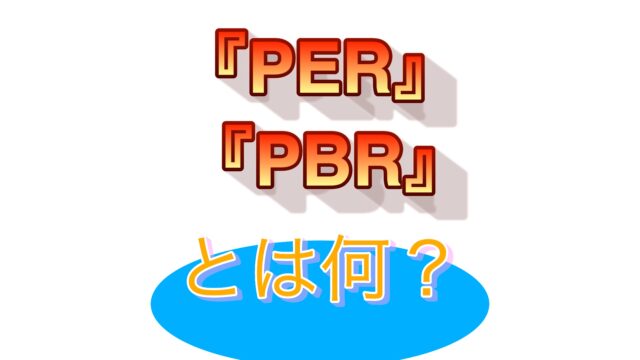失敗は財産、責めるは人ではなく仕組み!組織を創るマネジメント術とは
今回のブログは、僕が一番心に留めていることである「失敗は財産、責めるは人ではなく仕組み」というメッセージを皆さんに全力でお伝えしたいと思います。特に、チームを率いる立場の方、あるいは将来マネジメントに関わる可能性のある20代〜30代の皆さんには、ぜひ心に留めておいてほしい考え方です。
結論から言うと、失敗が起きた時に個人を責めるのではなく、その背景にある「仕組み」や「プロセス」に問題がないかを検証する。
この視点こそが、組織を根本から強くし、持続的な成長を可能にする最強のマネジメント術として重要です。
なぜなら、人は誰でもミスをするもの。ミスをしない人間はいません!
しかし、そのミスを誘発する仕組みを放置すれば、同じ失敗が繰り返され、結果的に組織全体のパフォーマンスが低下してしまうからです。
責めるべきは「仕組み」や「プロセス」であって、ミスをした人そのものではありません!
僕がこれまで働いてきた経験上、数多くの停滞している組織を見てきました。
その職場の多くは、何か問題が起きるとすぐに「誰が失敗したのか?」といった犯人探しか、「人を責め立ててどうにかする」といったマイクロマネジメントをしていました。
するとどうなるでしょうか? メンバーは失敗を隠蔽しようとし、新しい挑戦を恐れるようになります。だってミスすれば怒られるのですから、ミスや失敗を隠したくなるのが人情だと思います。
これでは、組織は何も学べず、成長の機会を永遠に失ってしまいます。
対照的に、目覚ましい成長を遂げている組織は、失敗が起きた時に「なぜこの失敗が起きたのか?」「どんな仕組みがあれば防げたのか?」という問いを立てます。
一例として私の知り合いの社長から聞いた話をしようと思います。
ある大きなシステム障害が発生した際、その社長は技術担当者を責めるどころか、「この障害を引き起こした原因は、十分なテスト期間を設けなかった私たちのスケジュール管理の甘さだ」と自らに責任があるとし、すぐに再発防止のためのチェック体制やテストプロセスの見直しに着手しました。その結果、チームは萎縮するどころか、信頼関係が深まり、より強固なシステムを構築でき、無事会社としても組織としても成長していったのです。
社長が行った自責思考やその行動を聞いた時、私は「見習いたいなぁ」「こうなりたいなぁ」と、同姓でも惚れてしまうくらい魅力的に写りました。
ここまで聞いて
「なんとなく言いたいことは分かった」
「じゃあ、なんで人を責めずに仕組みを責めることが大事なの?」と疑問い思った方もいらっしゃるでしょう。
ここからは具体的にその理由を深掘りしていきましょう。
1. 心理的安全性の醸成と挑戦意欲の向上
みなさんは心理的安全性という言葉を知っていますか?
心理的安全性は、世界的IT企業グーグルが取り入れている考え方です。
職場やチームなどの集団の中で、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態を指します。他のメンバーから批判や罰を受ける心配なく、間違いや質問、アイデアを自由に発言できる環境のことを指します。
人を責めない文化は、チームにこの心理的安全性をもたらします。
メンバーは失敗を恐れることなく、自由に意見を出し合い、新しいアイデアを提案し、果敢に挑戦できるようになります。
結果として、個々のパフォーマンスが向上し、組織全体の創造性や問題解決能力が高まります。
2. 真の根本原因究明と再発防止
失敗を個人の責任にするだけでは、根本的な解決には繋がりません。
問題の多くは、情報共有の不足、不適切な手順、明確でない役割分担など、仕組みやプロセスに起因していることがほとんどです。
人を責めずに仕組みに目を向けることで、客観的に原因を分析し、より効果的な再発防止策を講じることができます。
3. 学習する組織への進化
失敗から学び、改善するサイクルを回すことで、組織は「学習する組織」へと進化します。
個人の経験だけでなく、チーム全体の知見として蓄積され、次に活かされるようになります。これにより、同じ失敗を繰り返すことなく、組織全体の知識とスキルが向上し、変化に強い組織が作られていきます。
4. 信頼関係とチームワークの強化
マネージャーが人を責めず、仕組みの改善に焦点を当てる姿勢は、メンバーからの信頼を勝ち取ります。
信頼関係が深まれば、チーム内のコミュニケーションが活性化し、互いに助け合い、協力し合う強いチームワークが生まれます。これは、困難な局面を乗り越える上で不可欠な要素です。
では、管理職やマネージャー、あるいはリーダーシップを目指す皆さんは、この「責めるは人ではなく仕組み」という原則を、日々のマネジメントにどう落とし込んでいけば良いのでしょうか?
僕から具体的な提案として以下の3つ挙げさせていただきます。
- 「失敗発生時の行動規範」を明確にする: 失敗が起きたら、まず「なぜ起きたのか?」「どのプロセスに改善の余地があるのか?」という問いから始めるルールをチームで共有しましょう。「誰がやったのか」ではなく「どうすれば次に防げるか」に焦点を当てる会議体を設け、記録に残すことも有効です。
- 「ヒューマンエラー」を誘発しない仕組み作り: ヒューマンエラーは往々にして、複雑すぎる手順、確認不足を招くシステム、情報共有の不備などが原因です。定期的に業務フローを見直し、マニュアルを整備し、チェックリストを導入するなど、人がミスをしにくい仕組みを積極的に構築していきましょう。
- 「ポジティブなフィードバック文化」を醸成する: 失敗を責めないだけでなく、成功体験や良い行動は積極的に認め、褒めることを意識しましょう。これにより、メンバーは安心して挑戦し、建設的なフィードバックを受け入れやすくなります。また、小さな改善点も見逃さず、常に「より良い仕組み」を目指す姿勢を共有することが重要です。
マネジメントとは、完璧な人間を求めることではありません。むしろ、不完全な人間が最高のパフォーマンスを発揮できるような、優れた「仕組み」と「環境」をデザインすることです。
それにミスした人自身を責めたり怒ったりするマネジメントは、その人個人、ひいては組織の成長する機会を奪ってしまいかねません。
そして(言葉が悪いですが)”短絡的で稚拙な”マネジメントだと、個人的に思っています。
失敗を個人の問題にせず、組織の成長機会と捉え、仕組みを改善していく。この視点を持つことで、みなさんのチームはきっと、どんな困難も乗り越えられる最強の組織へと進化していくはずです。
あなたのチームが、失敗を恐れず、常に学び、成長し続ける組織となることを心から願っています。