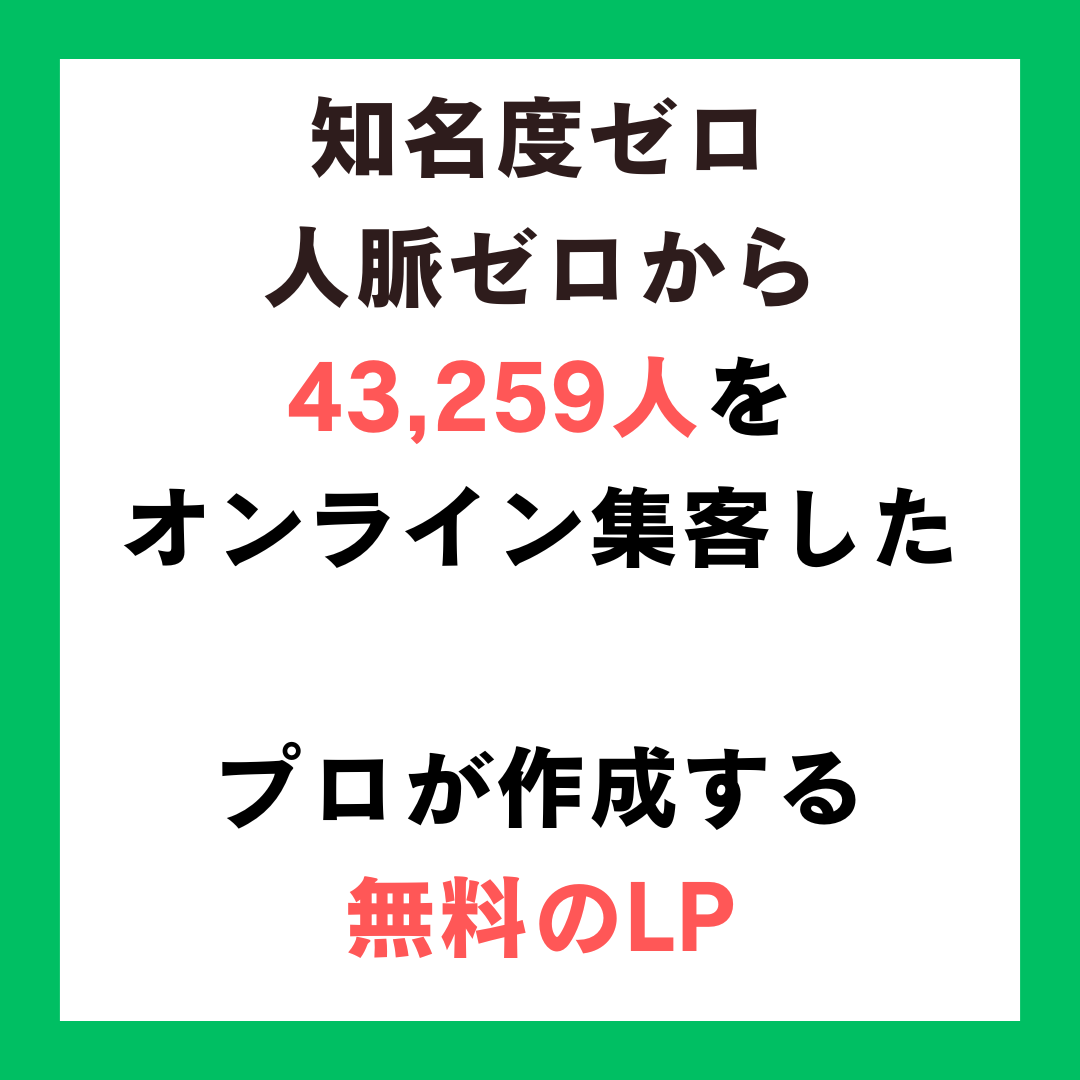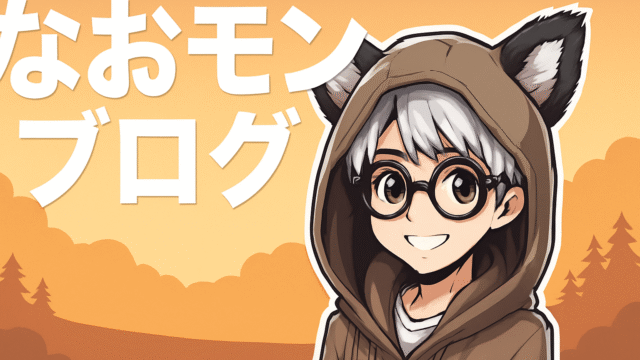スポンサーリンク
業績が低迷している企業にとって、どこから手をつけるべきか見当もつかないことがあります。
そこで注目したいのが「ABC分析」です。
とはいえ、急に「ABC分析」と言われても☹️「ナニソレ?」となるでしょう。簡単に言うとすると商品のランク付である「松竹梅」、とほぼ同じものという認識で良いと思います。
※豆知識:松竹梅のあとにも実はあり、「鶴亀」と続きます。縁起が良いですね〜
この手法は、経営資源を効率的に配分するための道筋を提供し、特に重要なアイテムに集中することで業績改善を図ることができます。
今回は、ABC分析の基本概念、進め方、具体的な活用方法について解説します。
スポンサーリンク
ABC分析とは?
定義と目的
ABC分析は、商品、顧客、業務データを「重要性」に基づいてグループ分けする手法です。その根底には「パレートの法則」があり、全体の80%の成果が20%の要素によって生み出されるという考え方が含まれています。
- Aグループ: 売上や利益の大部分を占める上位20%の項目
- Bグループ: 中程度の貢献度を持つ30%の項目
- Cグループ: 貢献度が低く、見直しが必要な50%の項目
ABC分析の進め方
ステップ1: データ収集
売上データや顧客データを収集し、具体的な指標を設定します。
ステップ2: データ分析
収集したデータを貢献度順に並べ、累積比率を計算してA・B・Cグループに分類します。
ステップ3: グループ分け
累積値に基づいて上位20%をA、次の30%をB、残りをCに分類します。
ABC分析の具体的な活用法
商品戦略の最適化
- Aグループ: このグループの商品に焦点を当てて販促活動を強化します。特別なディスカウントやプロモーションを行うことで、さらなる売上の向上を目指します。
- Cグループ: このグループの商品は、見直しや不要な在庫の削減を検討し、効率的な在庫管理を行います。
顧客戦略の強化
- Aグループ: 売上貢献度が高い優良顧客に対して手厚いアフターフォローや特別サービスを提供することで、ロイヤルティを高めます。
- Cグループ: 利益貢献度が低い顧客へのアプローチ方法を見直し、場合によっては対応コストを削減する判断をすることも検討します。
在庫管理の効率化
- Aグループの商品は適正在庫を維持し、Cグループの不良在庫は早期処分を検討します。これにより、保管コストを削減し、キャッシュフローを改善します。
成功事例
ABC分析を導入した企業では、A商品が売上の85%を占めることが明らかになり、マーケティング施策を強化した結果、利益が40%増加するなどの成功事例も報告されています。
まとめ:今日から始めるABC分析
ABC分析は、企業の成長戦略を練り直す強力な手法です。
業績が低迷している企業は、まずデータを見直し、優先順位を付けて経営資源を集中させることが求められます。
この分析手法を実践することで、効率的な意思決定が可能となり、持続的な成長へとつながります。
行動を起こすことが、業績改善の第一歩となります。ぜひ活用してみてください!