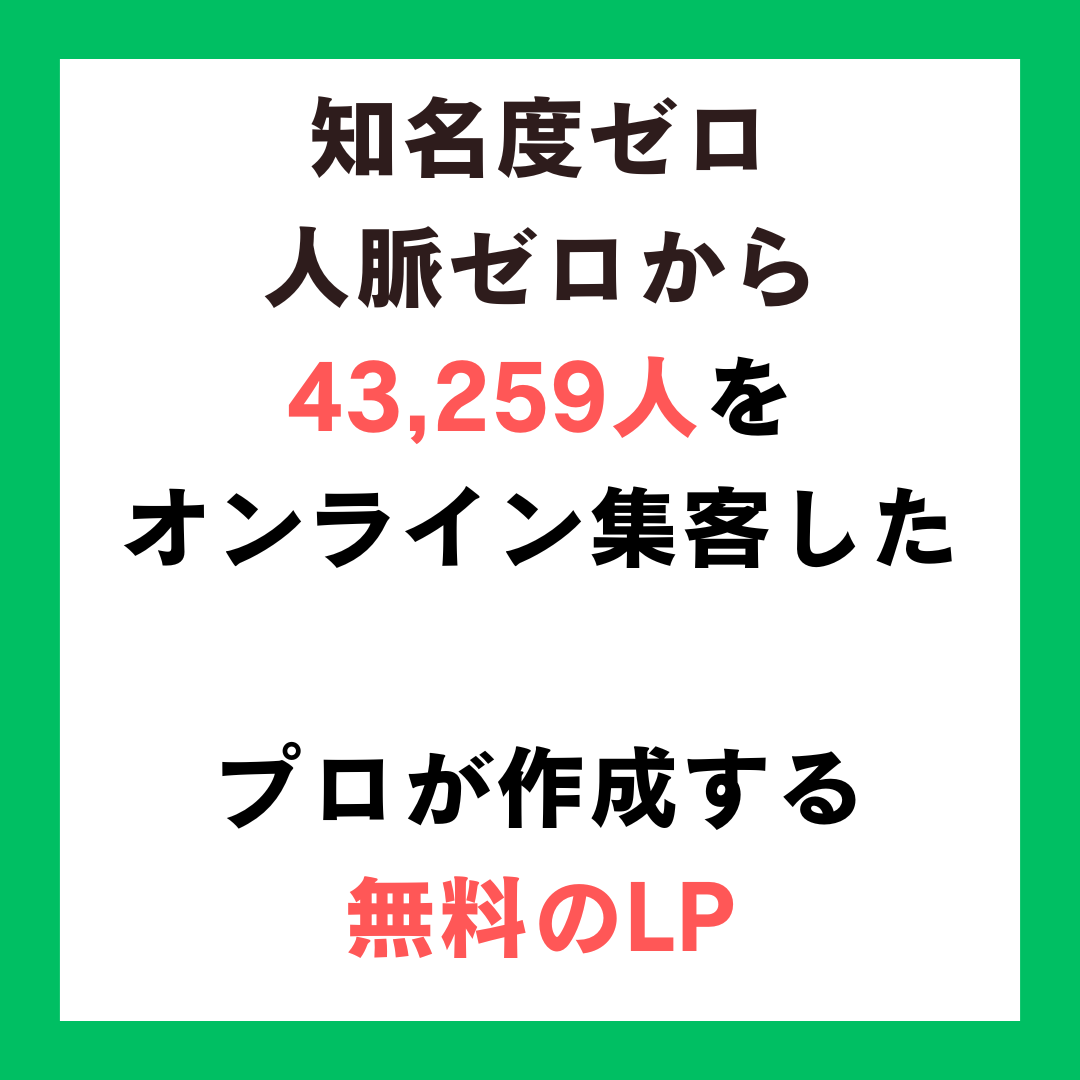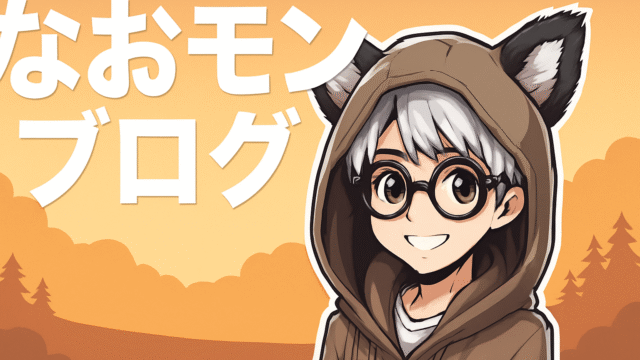スポンサーリンク
ある物事について十分な理解や全貌を把握しないまま、それぞれが自分の視点や一部分だけに基づいて意見を述べたり評価する状況。
このことは現代社会において遭遇することが多いと思います。
この状況を一言で言い表した言葉があって、「群盲像を評す(ぐんもうぞうをひょうす)」です。
古代インドの昔話に由来していると言われています。
言葉の成り立ち
- 由来
「盲人と象」という話は、古代インドのジャイナ教、仏教、ヒンドゥー教などに登場します。
この話では、複数の盲人が象に触れ、それぞれが触れた部分をもとに象について異なる意見を述べます。- 足を触った盲人:「象は柱のようだ」
- 尻尾を触った盲人:「象は紐のようだ」
- 胴体を触った盲人:「象は壁のようだ」
”どれも正しくて間違っている”そんな状況です。
- 比喩としての意味 この寓話は、「部分的な知識や経験だけで全体を評価することの危うさ」を象徴します。
「群盲像を評す」は、この話をもとにしたことわざや慣用表現であり、議論や意見の偏り、無知による誤解を指摘する際に使われます。
現代での使い方
- 批判的な文脈で用いられることが多い。
- 例:「専門家たちが今回の問題について議論しているが、まるで群盲像を評すようだ。全体像を誰も把握していない。」
- 学問や議論の場で、複数の視点の必要性を強調する際に使われる。
- 例:「どの分野の専門家も部分的なデータをもとに結論を出しているが、群盲像を評す状態にならないよう注意が必要だ。」
教訓
この表現は、物事を部分的な視点だけで判断する危険性を戒める教訓的な意味を持っています。
同時に、「異なる視点を組み合わせて全体像を把握する重要性」を示唆しています。
特に現代のように情報が多様化している社会では、この寓話が示す教訓が一層重要と言えるでしょう。
一部分だけをみて判断するのではなく、全体を俯瞰して重ごとを把握できるようになれると良いですね。