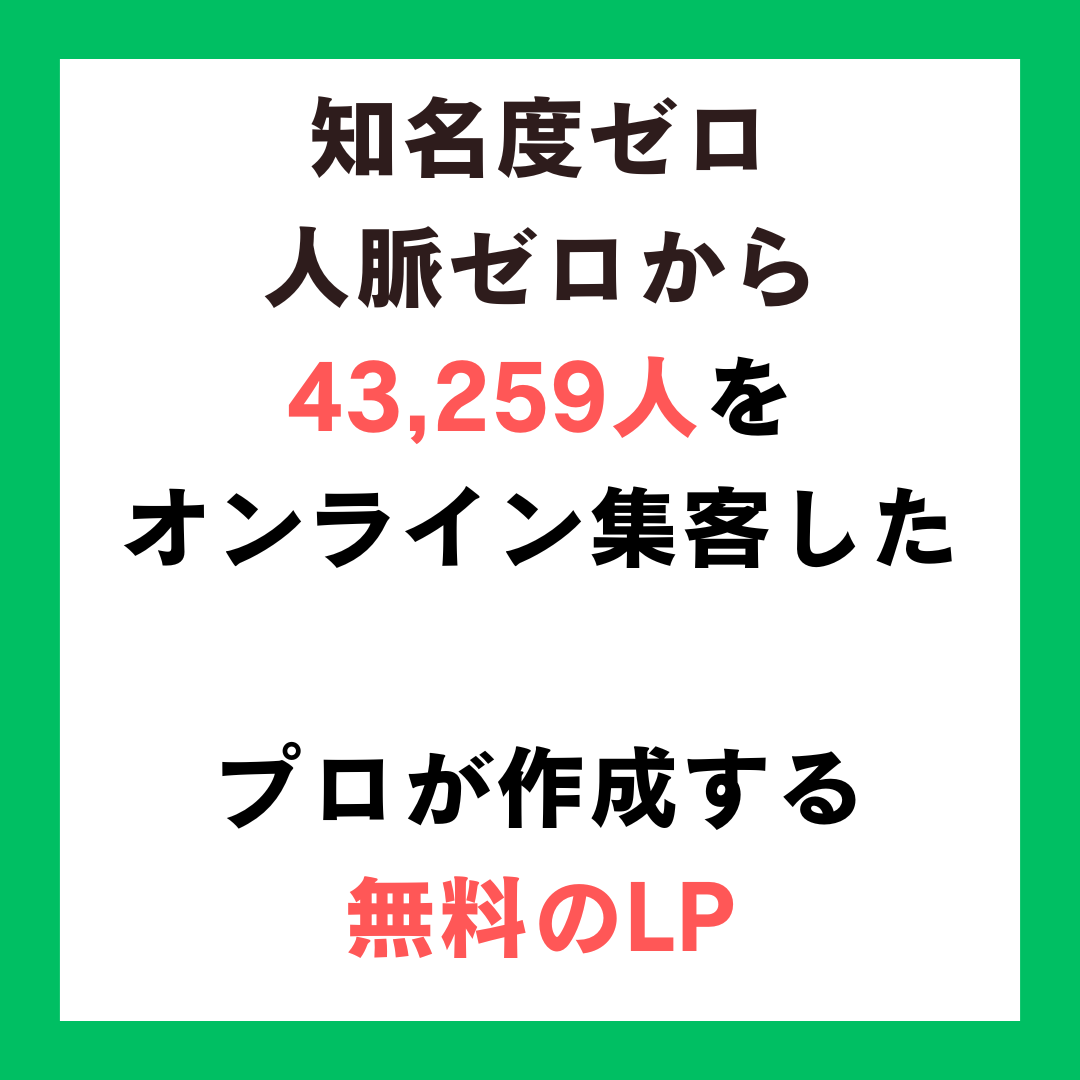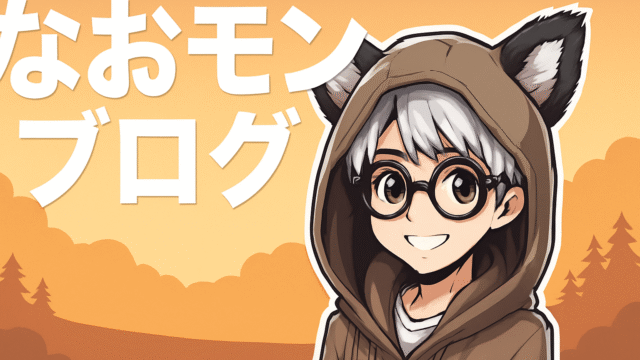【経営者必見】「利他」は100%利益相反する。それでも「利他経営」を続ける”やばすぎる理由”とは?
どうも、なおモンです。
みんなは、仕事で「利他」の心を持ててる?
自分のノウハウや知識を、周りの人に惜しみなく与えているだろうか。
「そんなことしたら、自分の優位性がなくなって、仕事が取られちゃうじゃん…」
「せっかく身につけたスキルなのに、簡単に教えたくない…」
そう思った人、安心してください。
その考え方、めちゃくちゃまともだ。
なぜなら、「利他」の心を持って行動すると、必ず「利益相反」が起きるから。
自分の利益を追求する「利己」の心と、誰かのために尽くす「利他」の心は、必ずぶつかり合う。
でも、俺は断言する。
「それでも、利他経営を続けるべきだ」と。
今回は先日見たYoutubeの動画、とある事業を経営するコンサル生と、コンサルタントの北原孝彦さんとのやりとりから、なぜ「利他経営」が、ビジネスを次のステージに引き上げる”最強の戦略”なのかを、俺の学びも交えながら解説していくよ。
「利益相反」は100%起きる
相談者は、自分の事業のノウハウを同業他社に公開することに抵抗を感じていた。
「せっかく積み上げたノウハウを公開したら、売上が下がるんじゃないか?」
この質問に対して、コンサルタントの北原さんは、こう断言した。
「利益相反は、100%起きる」と。
これは、非常にシンプルで、かつ真実だと思う。
自分の持っているものを他人に与えれば、一時的に自分の取り分が減るのは当然のことだ。
でも、それでもなぜ「利他」に徹するべきなのだろうか。
それでも「利他経営」を続けるべき理由
ここからが、今日みんなに一番伝えたいことだ。
一時的な利益相反を乗り越えて、なお「利他経営」を続けるべき理由は、大きく分けて3つある。
【理由1】新たな市場が生まれる
自分のノウハウを同業他社に与える。
一見、自分の首を絞める行為に見えるかもしれない。
でも、その瞬間、同業他社は「ライバル」から、あなたの「顧客」に変わる。
美容室を全国展開している北原さんの例がわかりやすい。
彼は、自社の美容室経営のノウハウを全て公開した。
結果、同業者から「どうやって経営しているんですか?」「どんな薬剤を使っているんですか?」と問い合わせが殺到し、ノウハウを学べるコミュニティや、薬剤販売といった新たなマネタイズの機会が生まれた。
ノウハウを売る側からすれば、それは事業の「次のステージ」だ。
目先のライバルを減らすことよりも、新しい市場を創り出すことの方が、はるかに大きなリターンを生む。
【理由2】業界全体を良くする「大義」が生まれる
自分の利益のためだけに仕事をしていると、どうしても思考が小さくなる。
でも、業界全体を良くするための「利他」的な行動を始めると、その事業には「大義」が宿る。
「私たちがノウハウを公開することで、この業界全体の質が上がり、お客様がより満足するようになる」
こんな「大義」を持つことで、それに共感する人が集まり、コミュニティが形成され、新たな仕事や営業の機会が生まれる。
そして、最終的に同業他社と協力し合う関係になれば、それはもはや「利益相反」ではなく、事業を拡大し守る「防流」に変わる。
【理由3】人が集まる「器」になる
ノウハウを惜しみなく与える人は、多くの人から「この人は信頼できる」「この人と一緒に仕事をしたい」と思われる。
そうして人が集まり、その人の周りにコミュニティができる。
人が集まれば、お金も集まる。
これは、ビジネスの真理だ。
【辛口反論】「でも、俺には守るべきものがある」
「そんなきれいごと言われても、俺には守るべき社員がいる。彼らを食わせていくためにも、まずは数字を追うのが経営者の務めだろ?」
うん、その意見は本当に正しい。
俺も、経営者として、社員を守るために利益を出すこと、数字を叩き出すことの重要性は、痛いほど理解している。
だからこそ、「利他」に徹することは、目先の利益を捨ててしまうことではない。
むしろ、長期的な視点で、より大きな利益、そして「大義」を追求するための、戦略的な選択なんだ。
まずは、「できること、リスクなく」始められることから、少しずつ「利他」の精神で行動してみよう。
まとめ
今回は、「利他経営」と「利益相反」の考え方について話してきた。
- 「利他」の行動は、100%利益相反が起きる。
- それでも「利他経営」を続けることで、新たな市場が生まれ、事業が「次のステージ」に引き上げられる。
- ノウハウを公開することは、業界全体を良くするための「大義」となり、人が集まる「器」を創り出す。
もし、今の事業が頭打ちだと感じているなら、一度立ち止まって、「どうすれば、自分のノウハウを、周りの人に与えることができるか?」と考えてみてほしい。
その視点の転換が、君のビジネスを、そして人生を、大きく変えるかもしれない。