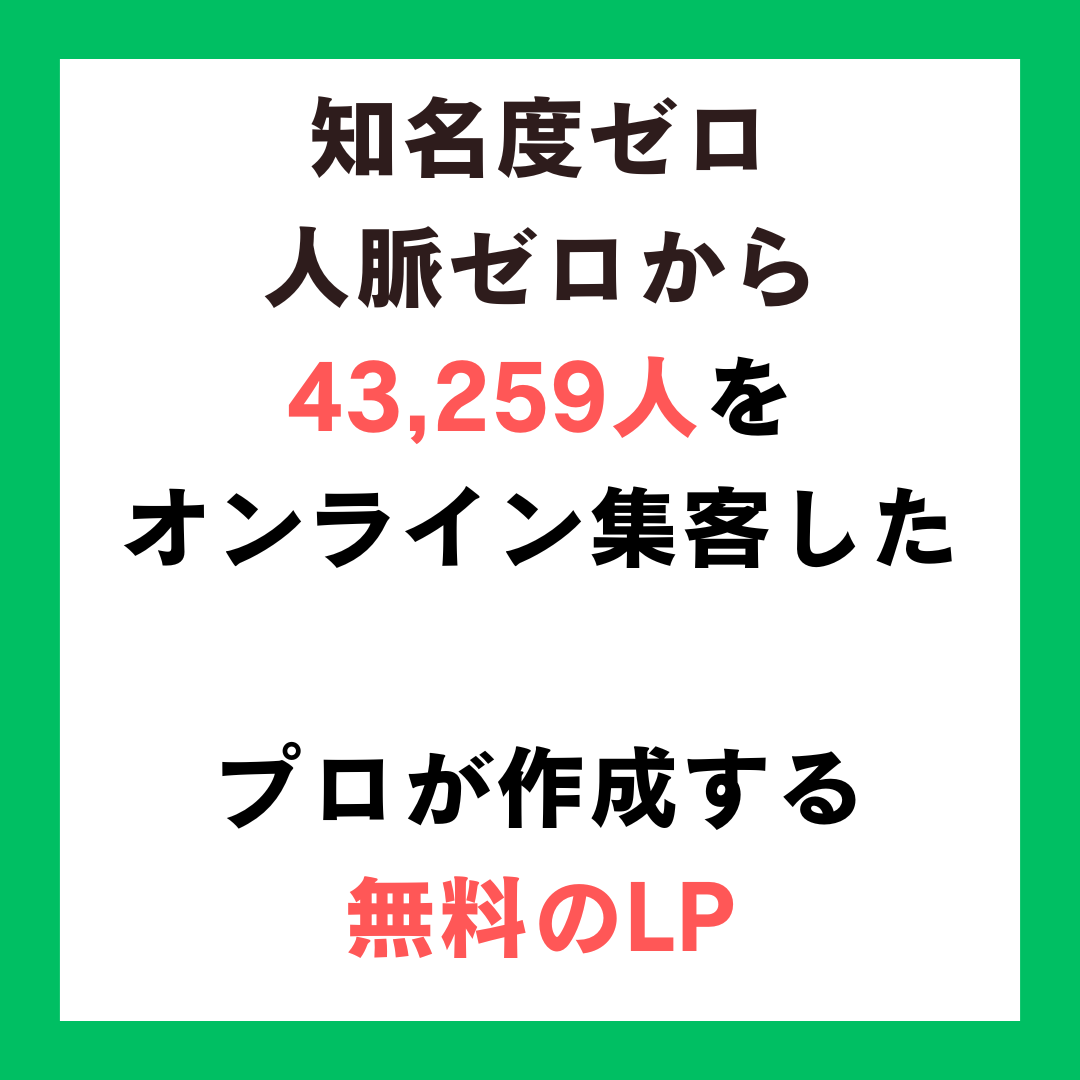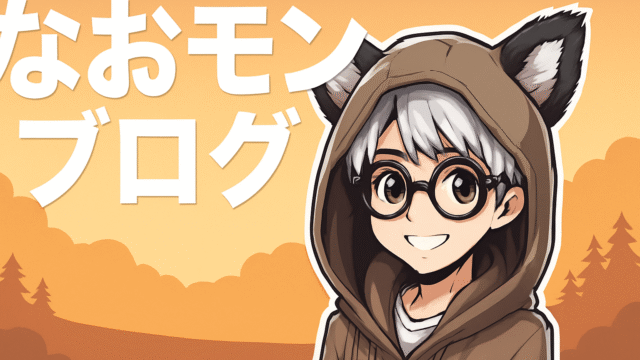社長、ヤバいかも?減価償却のウラ側を知らないと、銀行から「無能」の烙印を押されます
社長、経理、個人事業主、フリーランス。
みんな、自分の会社や事業の「減価償却」について、ちゃんと理解できてるか?
俺も昔はさ、減価償却なんて「なんかよくわかんないけど、経費になるやつ」くらいの認識だった。
ある日知り合いの経営者から、「会社の財務状況を銀行員に見せたら、めちゃくちゃ厳しい顔をされた」って聞いたんだ。
「この減価償却の仕方だと、うちとしてはちょっと…」
って言われたんだって。
「え、なんで?」って聞いても、なんか専門用語ばっかりでよくわかんない。
結局、そのときは融資してもらえなかったんだ。
後からわかったんだけど、減価償却をどうやっているかって、銀行から見たら、その会社の「信頼性」を測る、めちゃくちゃ重要な指標だったんだよ。
今日の話は、そんな失敗をしないために、減価償却と銀行の「超リアルな関係」について、わかりやすく解説していく。
減価償却って、利益を調整するための「小細工」じゃない
まず、減価償却の基本的な話から。
減価償却ってのは、例えば3000万円で買った車を5年使うとして、毎年600万円ずつ「費用」として計上できる仕組みのこと。
これって、会計上は「任意」なんだ。
だから、赤字になりそうな年に「減価償却をしない」ことで、一時的に見かけ上の利益を出すこともできる。
税理士の方によっては「今期は赤字になりそうだから、減価償却を調整しましょうか」って提案されることがあるらしい。
でも、これは絶対にやっちゃいけない。
なぜかっていうと、銀行はそんな小細工、全部お見通しだからだ。
銀行が見てるのは「頭隠して尻隠さず」
銀行員は、決算書を見た瞬間に「ああ、この会社は赤字を隠すために減価償却を調整してるな」ってすぐわかる。
まるで「頭隠して尻隠さず」だ。
減価償却費を計上してもしなくても、銀行は「フリーキャッシュフロー」っていう、減価償却費を足し戻したお金で、会社の本当の返済能力を判断してる。
つまり、減価償却を調整しても、銀行の評価はびくともしないってこと。
それどころか、「この社長は小細工する人だな」って、信頼を失うだけなんだ。
だから、赤字になるべき時は潔く赤字を出す。これが、銀行との信頼関係を築く第一歩なんだよ。
社長、その「設備投資」は本当に大丈夫?
減価償却って、建物や車、機械装置などの「事業投資」に対して行うものだ。
銀行員は、その投資が「売上と利益にちゃんと繋がってるか?」をめちゃくちゃ厳しく見てる。
- 儲かってもいないのに、見栄を張って本社ビルを建てる
- 使ってもいないのに、最新鋭の機械を大量に導入する
こういう、収益に結びつかない過剰な設備投資は、銀行からの評価がガタ落ちする。
まるで「浪費家」ってレッテルを貼られるようなもんだ。
だから、何か大きな買い物をするときは、「その投資がどれだけ利益に貢献するのか?」を具体的に説明できるようにしておこう。
融資期間でバレる、社長の「自信のなさ」
もう一つ、銀行員がチェックしてるのが「融資期間」だ。
減価償却のセオリーとして、融資期間は「減価償却の年数以内」に設定するのが基本。
例えば、耐用年数5年のトラックを買うなら、融資期間も5年以内にする。
逆に、耐用年数5年の機械なのに、無理やり10年で借り入れようとすると、銀行員から「この社長、本当に返済できる自信あるのか?」って思われちゃう。
これって、自分の事業に対する「自信のなさの表れ」なんだ。
事業がうまく回るなら、5年で返済できるはずだろ?
できる社長は、あえて減価償却期間より短く設定して、返済が終わった後にそのキャッシュフローをストックして、次の投資に備えたりもする。
銀行員は、そういうところをちゃーんと見てるんだぜ。
【まとめ】今日からできる、減価償却で失敗しないための5つのチェックリスト
減価償却は、ただの経費計上じゃない。
それは、銀行や世間に対して、「うちはこの設備投資で、これだけ儲けますよ」っていう、事業計画のプレゼンなんだ。
もし今、自分の会社の設備投資や減価償却について不安があるなら、以下の5つのポイントをチェックしてみてほしい。
- 物件(対象物)の明確化:いつ、いくらで買うのか、ちゃんと説明できるか?
- 売上と利益への貢献度:その投資が、どうやって売上や利益に繋がるのか、具体的に言えるか?
- 法定耐用年数の遵守:減価償却の年数と融資期間が適切か?
- 資産の現状把握:買ったはいいけど、使ってない機械はないか?使ってないなら、売れるうちに売却して資金に変えよう。
- フリーキャッシュフローの意識:見かけの利益じゃなくて、減価償却費を足し戻した「本当のお金」で、事業を回せているか?
減価償却で小細工したり、自信のない融資を組んだりするのは、もうやめようぜ。
正直に、堂々と事業をやる。
それが、銀行からの信頼を勝ち取る、一番の近道だ。