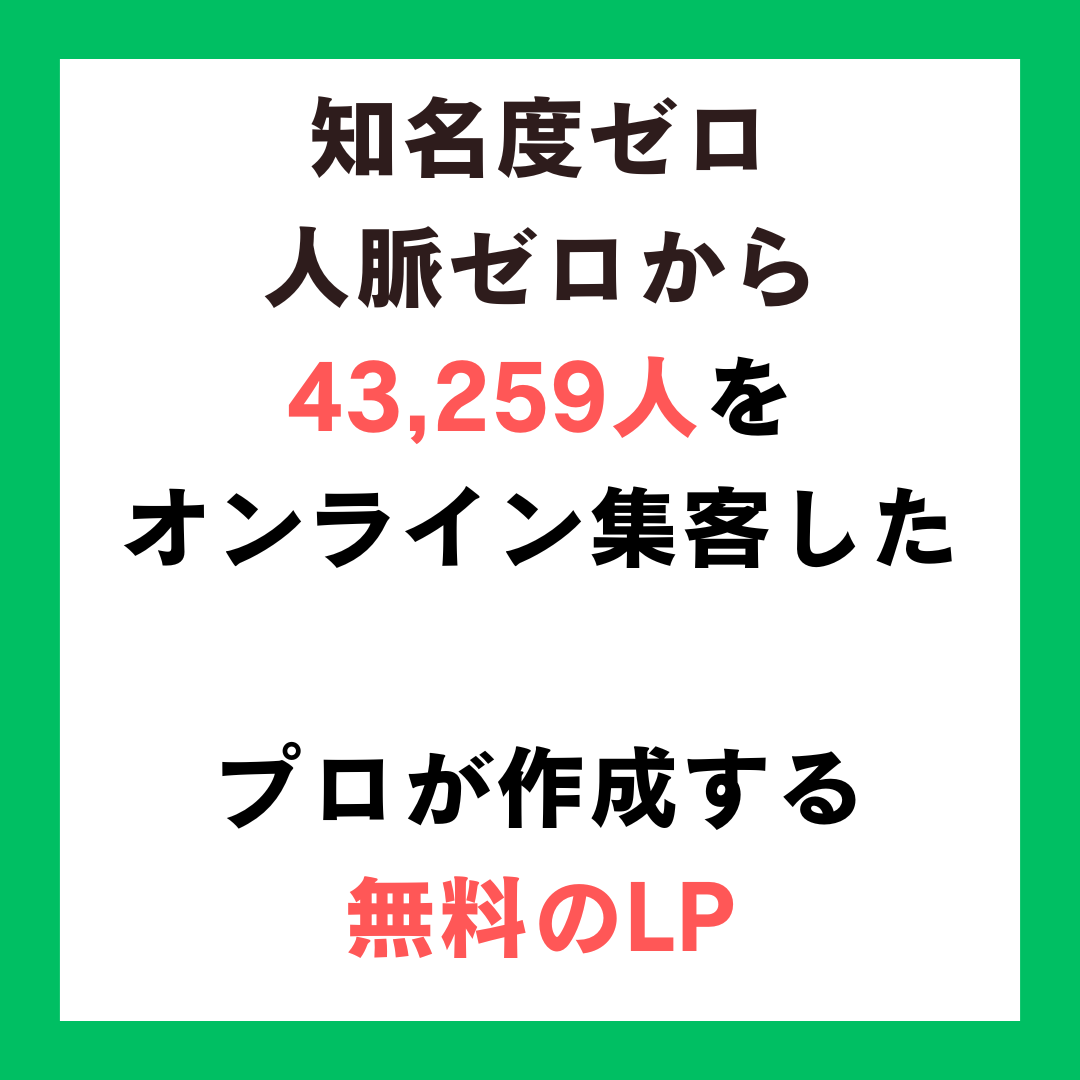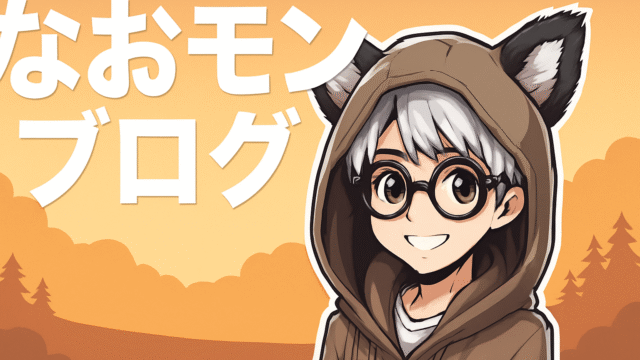「俺はどっちだ?」社長はプレイヤーかマネージャーか?“意識高い系”起業家が知らない泥臭い現実
どうも、なおモンです。
みんなの会社に社長はいる?愚問だよな、基本的に会社には代表(社長)っているもんな。
ここで言いたいのは、みんなの職場に社長がいて一緒に仕事をしているか?、ってこと。
「うちの社長、全然現場に出てこないんだけど、何やってんだろ?」
「あの人、いつもふんぞり返ってて羨ましいわ〜」
「俺もいつか社長になって、何もしないで稼ぎたい!」
…って、一度は思ったことない?
俺も昔はそうだった。
なんか海外でバカンスしながらリモートで指示出す、みたいな「何もしない社長」に憧れてた時期があったんだ。
でも、最近色々な社長さんと話す機会が増えて、気づいたことがある。
「何もしない社長」なんて、この世には存在しない。
彼らはみんな、俺たちが想像もつかないくらい、泥臭い努力をして、見えないところでめちゃくちゃ働いているんだ。
じゃあ、社長の役割って、一体何なんだろう?
現場で働く「プレイヤー」なのか、それとも全体を指揮する「マネージャー」なのか。
実はこれ、「業種による」、そして「会社のステージによる」っていう、めちゃくちゃシンプルな答えにたどり着いたんだ。
社長が「プレイヤー」であるべき業種
まず、社長が現場でバリバリ働く「プレイヤー型」が向いている業種。
それは、個人の能力やブランドが、そのまま商品の価値になるような仕事だ。
- 医者、弁護士
- コンサルタント、税理士、公認会計士
- デザイナー、アーティスト
こういう仕事って、お客さんは「その会社のサービス」じゃなくて、「その人自身」に価値を感じてお金を払ってるんだよな。
たとえば、イチローから野球を教わりたいと思ってるのに、会社の社長になったイチローが「うちのコーチを紹介します」って言ってきたら、「いや、俺が求めてるのはイチローなのに!」ってなるでしょ。
俺もブログやSNSで情報発信してるから、まさにこのプレイヤー型。俺が発信するからこそ価値が生まれると思ってるし、もし俺が「もうブログは書かないで、マネジメントに専念します!」ってなったら、みんな離れていくだろうな。
プレイヤー型社長である限り、会社の規模を大きくするのは難しいかもしれない。だけど、その代わり、お客さんとの信頼関係はめちゃくちゃ強固になる。
社長が「マネージャー」であるべき業種
一方で、社長が全体を俯瞰して指揮する「マネージャー型」が向いている業種。
それは、マニュアルや仕組みで、ある一定の品質を保てるような仕事だ。
- 小売業(スーパー、家電量販店)
- 製造業
- 介護事業
このタイプの仕事は、お客さんは「誰が売るか」じゃなくて、「何を、どんな品質で手に入れるか」が重要。
例えば、スーパーで野菜を買うときに、「この野菜は社長が仕入れたから美味しい!」なんて思わないよね。大事なのは、品質管理がしっかりしてるか、ってこと。
こういう業種では、社長が現場から離れてマネジメントに徹することで、会社の規模をどんどん大きくできる。
仕組みを作って、社員を増やして、シェアを拡大していく。そのためには、社長が現場で一つ一つのタスクをこなすよりも、全体を見て戦略を練る時間が必要になる。
社長が「マネージャー」に移行するタイミング
じゃあ、いつ「プレイヤー」から「マネージャー」に移行すればいいんだろう?
これは、会社の成長ステージによって変わってくる。
ベンチャー企業の若手起業家が、最初からマネージャーになろうとしても、まずうまくいかない。
なぜなら、まだ会社には仕組みもなければ、優秀な部下もいないから。
社長は、最初は間違いなく「最強のプレイヤー」であるべきなんだ。
誰よりも泥臭く、誰よりも汗をかいて、会社を牽引していかなければならない。
じゃあ、いつからマネージャーにシフトしていくか?
一つの目安は、社員が10人を超えたあたり。
この頃から、少しずつ現場の仕事を優秀な社員に任せていく。
そして、この「優秀な社員を育てる」ってのが、マネージャー移行の絶対条件なんだ。
社長の仕事を100%完璧にこなせる人はいない。でも、社長の仕事の70〜80%を任せられる「右腕」や「左腕」を育てることができれば、社長はマネジメントに集中できる。
しかも、社長と真逆のタイプ(営業が得意な社長なら、財務が得意な幹部)を育てることで、会社の弱点を補完できる。
批判的な意見への反論
「でも、俺の憧れの社長は、何もしないで悠々自適に暮らしてるって言ってたよ?」
…それ、本当に「何もしてない」と思う?
その社長は、すでに巨大な会社を築いていて、その会社には「強固な仕組み」ができあがってるはずだ。
彼らが「現場に出ない方が良い」って言うのは、そのステージに達したから言えること。
仕組みづくりが終わっている会社は、一種の到達点に達している。と個人的に思っている。
ゼロから会社を立ち上げる若手起業家が、その言葉を鵜呑みにして「楽をしよう」と思ったら、まず失敗する。
「ふんぞり返っている」ように見える社長だって、見えないところでとんでもない努力をしてるんだ。
そして散々努力した後の結果が、今の状態ってわけ。
資金繰りのために頭を下げたり、社員の人生を背負うプレッシャーに耐えたり。
俺たちが憧れるような成功の裏には、必ず「泥臭い現実」があるってことを、絶対に忘れないでほしい。
まとめ:「プレイヤー」と「マネージャー」を使い分ける
社長の役割は、あなたの業種と会社のステージによって変わる。
- 創業期は、社長自身が「最強のプレイヤー」として現場を引っ張れ。
- 社員が増えてきたら、「優秀な幹部」を育てて、少しずつ現場を任せろ。
- 会社の規模が大きくなったら、「マネージャー」として全体を指揮しろ。
このステップを理解せずに「楽をしたい」という甘い考えでマネージャーを目指すのは危険だ。
まずは、目の前の仕事に誰よりも真剣に向き合い、泥臭く結果を出すこと。
それが、いつかあなたが「何もしない社長」に憧れるのではなく、「俺がこの会社を引っ張っていくんだ」と自信を持って言えるようになるための、唯一の方法なんだ。